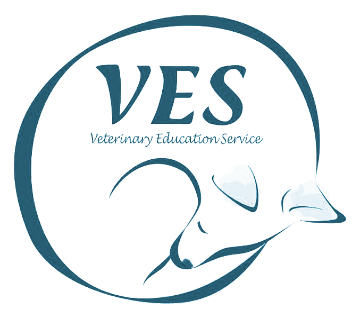2020.05.17
第52回 獣医麻酔:糖尿病麻酔について②

糖尿病では循環血液量は減少しているのか?
結論:そういうときもある
となります。
獣医麻酔だけでなく、集中治療領域でも特に重要となりますので、
理論的な背景を考えてみましょう!

本来は血中にグルコースがあればインスリンの作用によってそのエネルギー源が細胞内にも供給される。
血中のグルコースは本来は糸球体でろ過された後に、近位尿細管でほとんど再吸収される。
しかしそのグルコースが過剰となると再吸収量を超えてしまい、尿中に排泄されます。
いわゆる閾値を上回るんですね。
一般的にはグルコースが犬180mg/dl、猫300mg/dl以上で尿糖が出ると言われていますね。
こうなると浸透圧の関係で尿中に多量の尿が排泄される。この時に排泄されるのは自由水だけでなく、多量の電解質も排泄されてしまいます。
したがって失った体液量を補うために多飲となります。
しかし、なにかしらの原因で飲水ができない、もしくは術前の絶飲食によって想像以上に体液量が減少する可能性もあります。
糖尿病動物では細胞外脱水および細胞内脱水ともに生じているのです。
ここで注意が必要です。
教科書などでは、この辺が取り上げられるので、
糖尿病動物=脱水
と安易になりがちなのですが、動物によって体液量は様々です。
せっかくVESのブログに来てくれた皆さんは、安易な判断はせずに、症例に寄り添ったボリュームステータスを評価してあげてくださいね。
そして、脱水があるなら、
絶対に輸液補正してください。
脱水がシグナルとなり、有効循環血漿量が低下し、交感神経系が活性化します。
つまりカテコラミンが分泌されて、血糖値が上昇します。
この状態でも、尿中に多量に尿が排泄されているならば高いなりに血糖値は維持されますが、麻酔中、出血による循環血液量減少や血管拡張による臓器灌流低下によって、糸球体ろ過量が減少すると、グルコースは排泄すらできなくなってしまう。