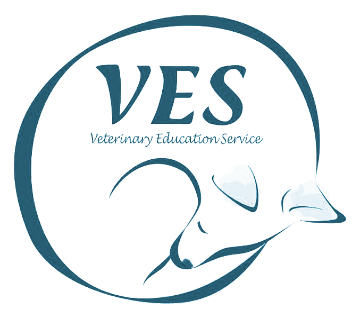2020.05.19
第54回 獣医麻酔:糖尿病麻酔について④

異常が出るのはカリウムとリン酸だけではないのです。
一番重要な電解質は、
ナトリウムですね!
糖尿病の場合は、血糖上昇による細胞内から細胞外への自由水の移動が生じるため、相対的にナトリウムが低く見えるとされています。


では、体内の総ナトリウム量はどうなっているのでしょうか?
実は、ナトリウムも相当失われています。
図の右側で細胞外の浸透圧が上昇しているため、この状態で利尿がかかってしまいナトリウムも同時に排泄されてしまいます。
一般的には、血糖が100mg/dl増加すると、ナトリウム濃度は1.6mEq/L下がるとされています。
例えば血糖値が500mg/dlだった場合、
1.6×5=8.0mEq/L低下するので、血液検査の結果、ナトリウム値が135mEq/Lであった場合は、
理論上、
135+8=143mEq/L
となり、これを補正ナトリウム濃度と言っています。
ちなみに、本来、高ナトリウム血症の場合、


だいぶ細胞内も脱水しているのですが、